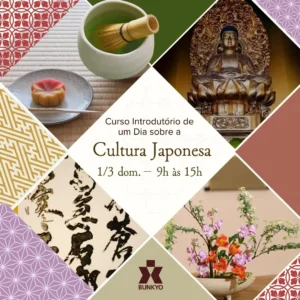記:2019年2月5日
350年以上の歴史をもつ大樋焼の十一代 大樋長左衛門(年雄)先生が、1月29日にブラジル日本移民史料館と日本館に来館し、大変貴重な大樋飴釉茶盌と大樋黒釉茶盌をそれぞれ贈呈下さいました。
大樋先生は、日本外務省の要請により、1月24日から30日までサンパウロに滞在し、アトリエ本間にてワークショップや、ジャパンハウスにて企画展示会および「宿る霊性 日本の茶道と工芸」をテーマに講演会を開催。ジャパンハウスに展示された3点の大樋焼を見るため来場した人数は、4日間で1万2430人を数えました。
そんなお忙しいスケジュールの中ご来館下さった大樋先生を、呉屋春美文協会長をはじめとする文協役員らが出迎えました。 大樋先生が移民史料館を一通りご覧になられた後、大樋飴釉茶盌の贈呈式が行われました。呉屋会長は「ブラジル社会における日本文化の継承と普及に大きく貢献いただいた」と、大樋先生のご厚意に対して感謝状を贈りました。
なお、 贈呈頂いた大樋焼飴釉茶盌は、現在リフォーム中のブラジル日本移民史料館7階の再オープニングセレモニーの際に展示する予定となっています。(4月末から5月頃に再オープン予定)
文協を後にした大樋先生はイビラプエラ公園内の先没者慰霊碑に向かわれ、その後日本館へ立ち寄られました。
日本館の展示品を一つ一つ丁寧に、また焼物などには解説も交えながらご覧になられました。日本館は65年前、茶道裏千家によって中南米で初めてお茶がたてられた場所であります。それもあって、裏千家代十四世家元および代十五世家元直筆の掛軸が飾られていますが、大樋焼は裏千家と大変縁が深く、また大樋先生御自身も裏千家の茶名を持たれていることもあり「ここで先生方の書を目にするとは」と、まるで見知らぬ土地で偶然に親しい恩師に実際に再会を果たしたかのような面持ちで「大樋焼は裏千家があってこそのもの」と強調されました。
大樋黒釉茶盌の贈呈式が行われた後は、日本館の役員でもあるシェーン氏による尺八が披露されました。
大樋先生の持つ和やかな様子が周囲にも伝わり、始終リラックスした雰囲気の中での贈呈式となりました。
大樋焼とは
石川県金沢市にある、350年の歴史と伝統をもつ楽焼の脇窯である。
江戸時代初期の寛文6年(1666年)、加賀百万石、加賀藩5代藩主・前田綱紀が京都から茶堂として仙叟(裏千家4代千宗室)を招いた際に、楽家4代一入に師事し、最高弟であった陶工・土師長左衛門が同道した。それを契機に、稀有な茶の湯の道具として発展し、綱紀公の強い意向もあり、加賀藩から手厚い保護を受け、現在に至る。
仙叟が帰京する貞享3年(1686年)後も長左衛門は残り、河北郡大樋村(現、金沢市大樋町)に居を構え、窯を建てて藩の焼物御用を務め、加賀藩より地名から大樋姓を許された。
大樋焼の制作活動は明治維新後、藩の御庭焼から民間の窯元として生業を立てざるを得なくなったことや、明治期動乱の茶道の衰退と重なって苦難の時期を迎えることになるが、後継の門人達、またその門人の子孫の制作活動の結果、飴色釉の特色ある稀有な焼物として全国的に知られるようになる。
金沢市橋場町に十代大樋長左衛門窯、大樋美術館がある。
—ウィキペディアより